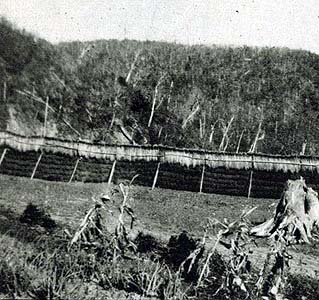ハッカ産業の誕生

薄荷の結晶(北見ハッカ記念館)
明治43年(1910)9月、小説家・徳冨蘆花は北海道旅行に行きました。旭川・神居古潭(かむいこたん)駅を出発し、名寄に向かう途中、シソでも麻でもない見知らぬ草が畑に干してあるのを見つけました。車中の人々があれは何だろうと話しているうち、誰かが「薄荷(はっか)ですよ」と教えてくれました。
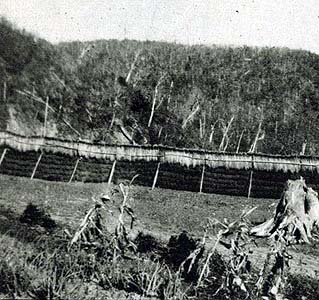
薄荷の乾燥
かつて薄荷は日本が世界に誇る農産物でした。なんと世界需要の9割が日本産だったのです。そして、圧倒的に強かったのが北海道の北見産。北見だけで世界市場の7割を押さえていました。薄荷は北海道に大きな富をもたらし、一種のゴールドラッシュのような状況を呈していました。
しかし、もちろん今ではほとんど生産されていません。いったいなぜか? 今回はハッカ産業の歴史です。

1975年に登場した高品質ハッカ「さやかぜ」
ハッカの存在は古く、紀元前3733年に完成したギゼーのピラミッドの建設時、労働者の食事にハッカが用いられたという記録があるそうですよ。
薄荷は英語でミントと言いますが、これはギリシャ神話から命名されました。
メンタというニンフ(妖精)が瞑府の王ハデスと不倫し、嫉妬に狂った王の妻から「草になれ」と踏みつけられると、メンタは爽やかな芳香を放つ草に姿を変えた、という話です。
ところが、この時代には、戦争中は食べるのも栽培するのもいけないと言われていたそうです。もちろん俗信なんですが、その理由をアリストテレスは「ハッカは体を冷やし、軍人の勇気と精神を冷やしてしまうから」と語っています(『疑問集』)。
新約聖書のマタイ伝とルカ伝では、イエスがパリサイ人(ユダヤ教徒)を「お前たちは薄荷や芸香(うんこう=ジンチョウゲ)などあらゆる野菜の10分の1税を納めているが、正義や神への愛がないがしろである」と批判しています。
さらに1世紀ローマの博物学者プリニウスは、『博物誌』で薄荷の薬効を100種類以上あげています。気つけ、胃病、腰痛、頭痛なんかはわかりますが、ヘビ毒とかコレラにも効くと思われていたようです。
いずれにせよ、昔から人々はスースーする歯磨きを使っていたわけですな。

『和漢三才図会』より薄荷のイラスト
日本にいつ薄荷が入ってきたかは諸説あるようですが、紀元前に栽培されていたとも、1200年頃に栄西が中国から持ち帰ったとも言われています。
ちなみに『日葡辞書』(1603〜04)には「Facca(ハッカ)」とあり、 「ある種の薬」と訳されています。
さらに『和漢三才図会』(1712年頃)には「人々は薄荷の葉を刻んで煙草の代わりに吸って咽喉や口歯の薬としている」とあるんですが、面白いのは次の解説。
《猫が薄荷を食べると酔う。それで猫に咬まれたときは、その汁をとって塗れば効がある。また、「薄荷は猫の酒である。犬は虎の酒である。桑椹(くわのみ)は鳩の酒である。ほう草は魚の酒である」という。いずれも物の相感作用によって酔うのである》
虎は犬を食べると酔っぱらうって、どういうことなんですかねぇ?

岡山総社地方の薄荷畑
さて、日本での本格的な薄荷生産は1817年、岡山の秋山熊太郎が江戸から持ち帰った日本薄荷の根を栽培したのが最初とされています。その後、各地に広がり、北見では明治20年代(1887〜)に栽培が始まりました。
薄荷の生産方法を簡単に書いておくと
①刈り取った草を1〜2週間乾燥
②水蒸気で蒸留すると取卸油(とりおろしゆ)という黄緑色の油がとれる。
③取卸油を遠心分離器で精製して、結晶(粗脳)と赤っぽい脱脳油(赤油)とに分離
④粗脳は再結晶させて無色針状結晶の薄荷脳(メントール)に。赤油は蒸留して透明なハッカ油(白油)にして商品化


(左)効率が3倍に上がった田中式蒸留器、(右)遠心分離器

原油から分離された粗脳

左から取卸油、薄荷脳、赤油、白油
薄荷を外国に輸出するにあたり、明治20〜30年代は外資のコッキング商会が関与していました。
その後、北海道の薄荷は大手商社の独占となり、異常な安値で取引されるようになります。農民の窮状を見かねた当時の上湧別村長が動き、ロンドンのサミュエル商会との間で直接取引することになりました。
大正元年(1912)、ハッカ業者1300名あまりの代理人とサミュエル商会は共同販売の契約を結びますが、この協定を探知した商社側が一斉に買い占めに入り、結局、サミュエル商会は大赤字になります。そして長い裁判闘争が始まります。
大正3年、第1次世界大戦の勃発でサミュエルが撤退すると、大手商社は価格協定により異常な安値で薄荷を買うようになりました。農民の苦しみは長く続き、これがホクレンの共同販売につながっていくのでした。

ホクレンの輸出ケース
前述したように、昭和12年(1937)頃には、日本は世界市場の9割を占める薄荷王国になりましたが、第2次世界大戦を経て、作付面積は激減。昭和30年代に一度盛り返しますが、結局、ほとんど栽培農家は消えていきました。
薄荷栽培が衰退したのは、メントールの化学的な合成が可能になったからです。
メントン、ピペリトン、チモールの還元、あるいはイソプレゴールへの水素添加など、さまざまな方法がありますが、特に致命的だったのは不斉合成(ふせいごうせい)の発明です。

ターペンタインから合成した人工ハッカ
通常、使われる薄荷の成分は「ℓ(エル)‐メントール」なんですが、異性体に「d‐メントール」と呼ばれるいやな臭いのする物質があります。違いは光を左右どちらに偏光させるかなんですが、この異性体から有効成分の合成を可能にしたのが不斉合成です。この技術によって、1983年にはメントールの量産化に成功します。
この技術を発明したのが野依良治博士で、2001年のノーベル化学賞を受賞しています。そして、博士が取締役を務める高砂香料工業は、現在でもメントールの圧倒的な世界シェアを握っているのでした。
制作:2010年10月10日
<おまけ1>
『日本後紀』によれば、815年、嵯峨天皇が近江国唐崎に行幸し、梵釈寺でお茶を飲んだと記録されています。
ただし、当時のお茶は中国の「団茶」に近いもので、蒸した茶葉を臼でついて乾燥させ、それを火であぶり熱湯で煮るものだとされています。湯の中には塩、葱(ねぎ)、薑(はじかみ)、棗(なつめ)、橘皮、茱萸(ぐみ)のほか、薄荷を混ぜていたそうです。なんかまずそうなお茶ですな(涙)。
<おまけ2>
北見の開拓が始まったのは明治10年(1897)。中心となったのは高知からの開拓移民団「北光社」で、初代代表は北海道開拓を夢見た坂本龍馬の甥・坂本直寛でした。
<おまけ3>
サミュエル商会の創業者であるユダヤ人のマーカス・サミュエルは、1833年、高校の卒業旅行として来日しています。横浜の三浦海岸で見つけた貝があまりにも美しく、貝殻を拾い集めて帰国、その後、貝殻細工の製造販売で財をなしてロンドンに商社を作るのです。それがシェル石油となりました。シェルのマークであるホタテ貝の源流は日本の貝殻だったんですな。