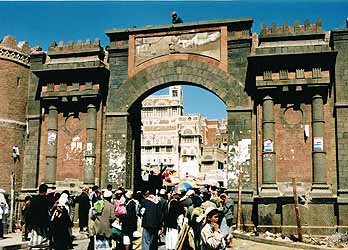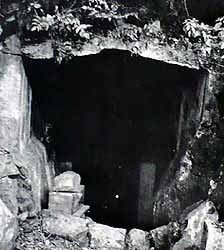アンチエイジング入門(笑)
不老不死の薬を探し出せ!

人魚の肉を食べれば死にません!
(和漢三才図会)
竹から生まれたかぐや姫は、求婚してきた5人の男それぞれに、「これを持ってきたら結婚してあげる」と高飛車なことを言いますが、それは「仏の御石の鉢」「火鼠の裘」「龍の首の珠」「燕の子安貝」、そして「蓬莱の玉の枝」という世にも珍しい品々でした。
蓬莱とは「方丈」「瀛州」(えいしゅう)と並ぶ三神山の1つで、ここには不老不死の仙人が住むとされていました。蓬莱は渤海湾とも台湾とも日本とも考えられています。

この海の向こうに不老長寿の王国が?
(天津郊外の渤海湾)
司馬遷の『史記』によれば、秦の始皇帝は「東方の三神山にある不老不死の霊薬をもってこい」と徐福に命令します。それで、日本の各地に徐福伝説が残っているのです。 最も有名なのは和歌山県の那智勝浦や新宮あたりですが、今回は静岡県島田市の蓬莱橋に行ってみましょう。これはギネスブックにも載っている世界最長の木造橋(全長900m)です。「長い木橋」は「長生き橋」に通じることから、有名な観光名所となっています。

世界最長の木造橋・蓬莱橋
でだ。
再び『竹取物語』に話を戻すと、結局独身のまま、ある日、月に帰ることになったかぐや姫は、去り際に御門に「不死の薬」と「天の羽衣」を贈ります。
この不治の薬は壺に入っているとだけ書かれていて、詳しい説明はありません。
では、この「不治の薬」の正体はどのようなものなんでしょうか。
あくまで一般論ですが、「不治の薬」にはだいたい3種類あります。「水銀」「ミイラ」「人魚の肉」です。今回は、この3つの薬をめぐって、世界をめぐります。
まず水銀ですが、これは中世ヨーロッパでも中国でも重要視されました。水銀と硫黄の化合物である硫化水銀は赤色(朱色)で、天然では辰砂(しんしゃ)といいます。
中世ヨーロッパでは、この辰砂からハリーポッターで有名な「賢者の石」が作られると考えました。賢者の石によって、卑金属が「金」に変わるとされたのです。これが「錬金術」ですな。
一方、中国では、辰砂から不老長寿の霊薬「仙丹」が作られると考えました。こちらは「錬丹術」と言います。

これが辰砂
中国では、始皇帝をはじめ、多くの皇帝が霊薬として水銀を飲み、苦しみながら死んでいきました。
もちろん日本でも水銀は重用されました。かの邪馬台国でも水銀がとれたと『魏志倭人伝』に書かれています。ちなみに日本では水銀を「丹」と書き、和歌山県の山奥にある丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)が水銀の神様の総本山です。多くの神社が朱色なのも、水銀を木の防腐剤として使ったからでしょう。
続いてミイラですが、これは文字通り人間のミイラのことです。粉末にして飲めば、不老不死の薬効があり、万病に効くと信じられていました。ちなみに江戸時代に代々、通訳(通詞=つうじ)を務めていた家で発見された古文書から、ミイラの輸入記録が見つかっています(2000年11月8日、朝日新聞)。
余談ですが、ミイラの語源は防腐剤として使われた樹脂ミルラ(没薬=もつやく)から来ています。その昔、俺は自分でミイラを作ろうと思って、わざわざイエメンに行って没薬を買ってきました。その現物はいま見当たらないので写真はないんだけど、イエメンでは市場のどこでも没薬と乳香(香水の原料)を売っていました。
さらに余談ながら、アラブ各国では魚のミイラの置物を売ってたりしますが、これは買わない方が無難です。俺が買った物は完全に乾いておらず、日本で異臭を放って大変でした。
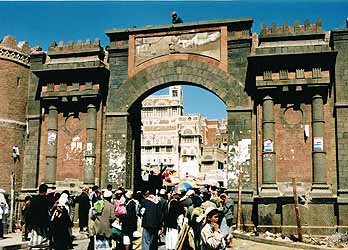
イエメンでもさすがに人間のミイラは売ってない
えっと、なんの話だっけ? えーと、「不治の薬」ですな。
3番目の薬は「人魚の肉」です。
これは八百比丘尼の伝説から来てるんですが、若狭国(福井県)の漁村で人魚の肉を盗み食いした娘が、そのまま10代の姿で800年生きた、という伝説です。全国を旅して、最後は福井県小浜市の空印寺の洞穴で死ぬんですが、なんと旅の途中に義経・弁慶の一行と出会います。
ちなみに義経の家臣の清悦もニンカン(人魚?)という皮のない朱色の魚を食べて400年も生きたとされています(『清悦物語』)。

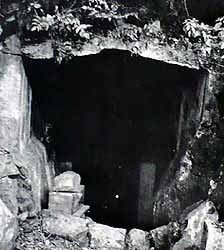
八百比丘尼の木像と、最期を迎えた空印寺の洞穴
古来、日本では多くの人魚が発見されました。
多分最古の目撃記録が推古天皇の612年(『聖徳太子伝暦』による)で、有名なのが619年(『日本書紀』)。『古今著聞集』(1254年刊行)では人魚について「かしらは人のやうにてありながら、歯はこまかにて魚にたがはず、口さしいでて猿ににたりけり」と書かれています。


文献に記録された人魚
1222年には、人魚が博多の海に流れつき、調査のため、冷泉中納言が来たことから、博多のことを「冷泉津」と呼ぶようになりました。冷泉町にある「龍宮寺」には、現在も人魚の骨が伝わっています。
ちなみにこの人魚ですが、江戸時代に出版された百科事典『和漢三才図会』に、オランダでは人魚の骨を解毒剤として使っていると書かれています。
余談ついでに、中国版百科事典『三才図会』では人魚は魚ではなく、「てい」(人偏のない「低」)という人間とされています。ということは、やっぱり人魚は実在したんでしょうか? それともジュゴンの見間違いなんでしょうか?

人なので食べてはいけません
さて、再び『竹取物語』に話を戻します。
かぐや姫からもらった「不死の薬」と「天の羽衣」を、御門は駿河国の日本一高い山で焼くように命じました。それで、その山は「不死の山」つまり富士山と呼ばれるようになりました。富士山からは、いつまでもいつまでも煙が上がり続けたと言われています。
制作:2007年12月17日
<おまけ1>
不老不死の薬とされた水銀は、金メッキに使われました。『東大寺大仏記』によれば、奈良の大仏を作るのに水銀5万8620両(約50トン)、金1万446両(約9トン)が用いられました。アマルガム法という合金技術で金メッキをしたわけですが、この大量使用によって、奈良には極めて甚大な水銀公害が発生しました。つまり、“水俣病”です。これが祟りだと思われ、平城京は見捨てられ、平安京が造営されたのでした(日本経済新聞2004年5月7日、白須賀公平氏の寄稿論文)。

奈良の都を水銀中毒にした?大仏様
<おまけ2>
古来、日本には海の彼方に不老不死の楽土(常世=とこよ)があると信じられていました(琉球では東方のニライカナイ)。
一方、仏教では不老不死の観音浄土は南の海上にあるポタラカ山だとされてきました。このポタラカは漢字で「補陀洛」と書き、海を渡って補陀洛を目指す修行を補陀洛渡海(ふだらくとかい)と言いました。
チベットのラサにあるポタラ宮はポタラカから来てるんですね。ちなみに日光もここから来ているとされます。
<ポタラカ→ポタラ→ふたら→二荒→日光>
世界は不老不死でつながっているのでした。

ポタラ宮。この地こそ不老不死の都か?